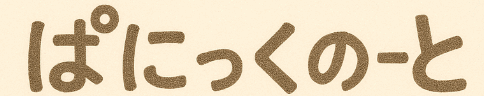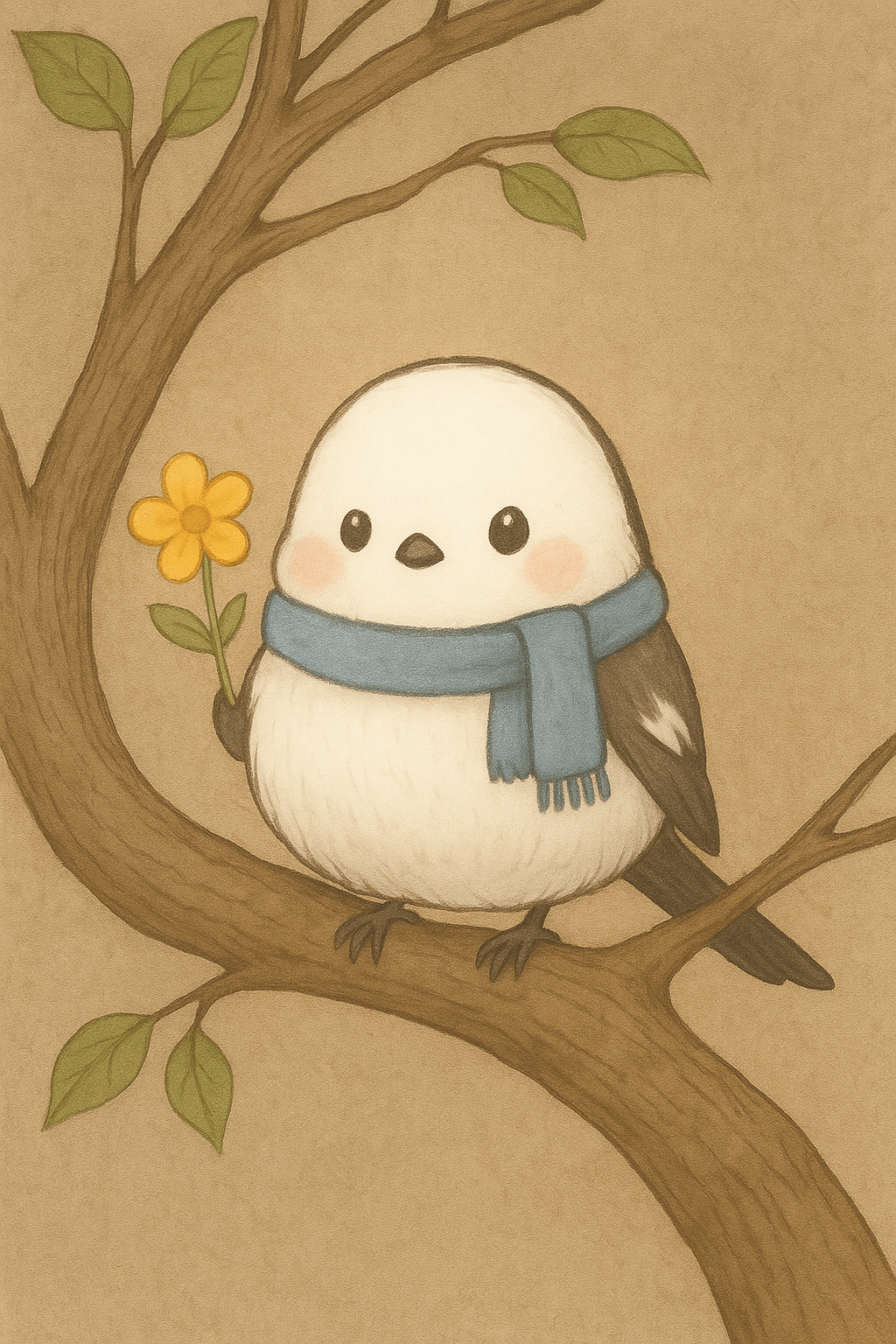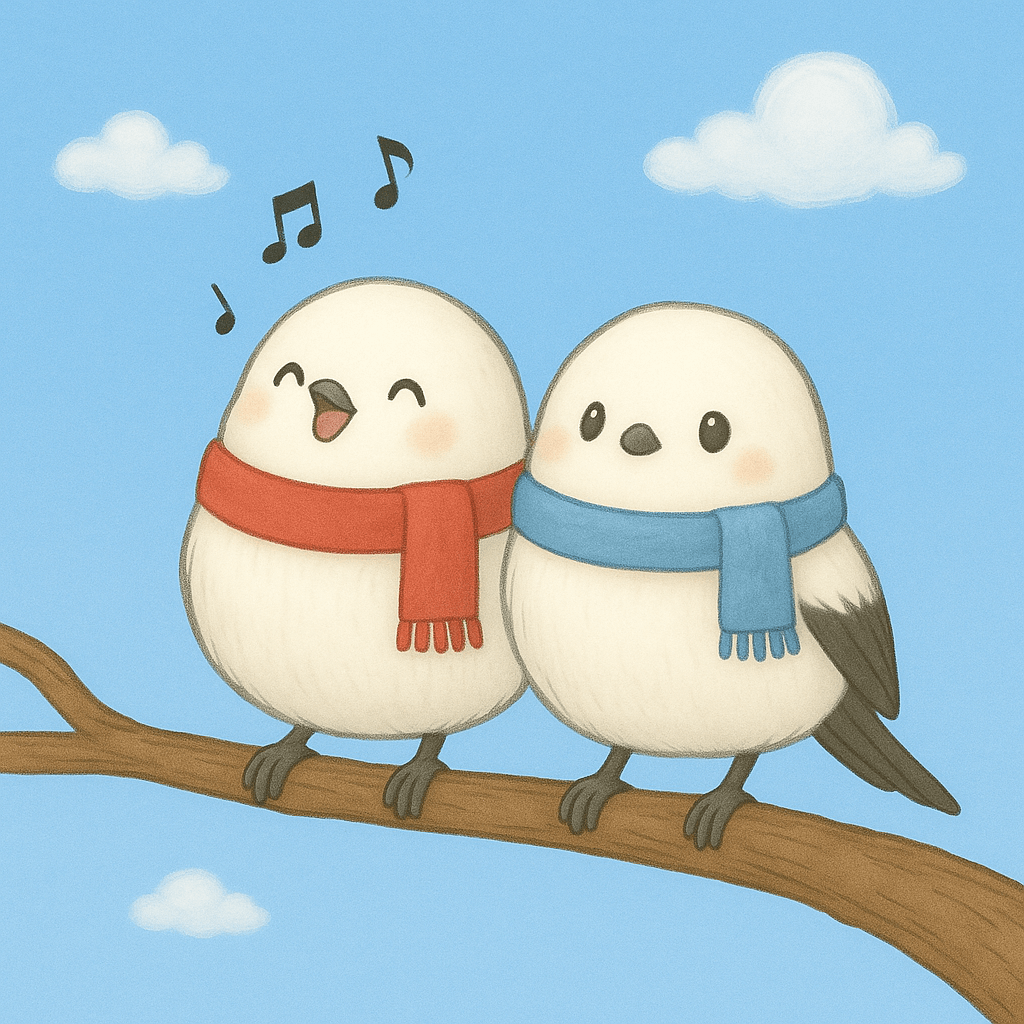自律神経のバランスが乱れることが私たちの身体や精神に様々な影響をもたらすことがわかったので、それならばそういう状態にさせないように努力すればいいのではないかと思い、今度はなぜバランスが乱れるのかを考えてみました😀
なぜバランスが乱れてしまうのか
私たちが心身共に良いコンディションで過ごせるのは、交感神経と副交感神経の二つの神経がバランスよく働いているからです 私たちは一日のうちに人それぞれいろんな活動をします 例えば大事な商談があったり、試験を受けたり、スポーツの試合があったり、工場で何かを作ったり・・・その時交感神経は優位となって血液循環や代謝を上げて活動性を高めてくれています でも誰もがそのまま活動しっぱなしではないのは、要所要所で副交感神経が身体の各部分の活動性を下げて、次の活動に備えて回復、修復させるために働いてくれているからです
二つの神経の理想的な働きは、緊張状態が続いて交感神経の働きが高くなった後に、副交感神経の働きが高まってリラックスした状態へとスムーズに切り替えられることです しかし、何らかの理由でその働きが十分に行われなかった場合に、自律神経のバランスに乱れが生じると考えられます😦
二つの神経をスムーズに働かせる
どうやらこの二つの神経がスムーズに働いてくれない状況にある時に、バランスも上手に取れないのではないかと考えられます ですから、その状況をなるべく作り出さないようにすればいいということなのでしょうが、そんな簡単な話ではないのはわかっています(^_^;) 私たちはいかに自律神経が問題なく働けるかを頭に入れながら、日々生活していくのが望まれることだと思います
私たちが自律神経のリズムを乱さないためには、規則正しい生活を送ることが大事です 自律神経は24時間の周期で、交感神経と副交感神経が状況に応じてオン・オフを切り替えながらバランスを保っていますが、 どちらか一方に大きく傾くのではなく、「平衡の状態を維持しながら状況に合わせてどちらかに少し優位になるパターン」 が理想的な状態と言われています そして、この24時間の睡眠、食事、運動、仕事、休息など..私たちが普段ルーティンで行っている日々の生活のリズムが乱れてしまうと、それが”自律神経のバランスが崩れるきっかけ”になるのです
私たちが自律神経のリズムを乱さないためには、規則正しい生活を送ることが大事であり、毎日生活する上でいかに生活リズムを壊さないかが重要になってくることがわかりました😄
では、生活リズムが壊れる原因について考えてみましょう😊
生活リズムが崩れる原因
生活リズムが乱れる原因としては、睡眠不足や不規則な食生活、ストレスなどが考えられます 昼夜逆転の生活をしていたり、慢性的な寝不足や食習慣の乱れなどは、生体リズムを狂わせます また、過労による肉体疲労や極度のプレッシャーなどもその原因になり得ます
限界を超えたストレスや睡眠不足、疲労などが積み重なると、アクセルが暴走し始めます 人の体の機能は24時間のリズムで働き、ストレスや環境の変化などに応じて微調整をしながら良い状態に保たれているのですが、睡眠時や食事の時なども、昼夜の変化に合わせて、体温やホルモンの分泌などを必要に応じて変化させています だから例えば、人が不眠不休で働いたりすると、脈拍や血圧が変動し呼吸が早くなったりしますが、それだけではなく、更に副交感神経を抑制して食欲低下や疲労回復の遅れを招いて、生活に支障をきたし始めるというわけです 生体リズムが狂ってしまうと、それが自律神経の乱れを招くことになるのです
と、書きましたが、なんでそうなってしまうのかとかいう詳しい働きは別にわからなくてもいいかと思います(^_^) 続いて原因となりうることも挙げてはおきますが、一読して ふ~ん、そうなんだと思ってもらえればいいと思います
他にも、偏った食生活によって、ビタミンやミネラルなどの身体の機能を調節する栄養素が不足することや、腸内環境が悪化することも自律神経の乱れの一つの原因になります
季節の変わり目…夏場は暑さに耐えれるように体温調節をしたり、日が長く活動時間が増え、他の季節より交感神経が優位に働いています 梅雨や台風などの気候による変化も自律神経に負担をかけます そして冬の寒い時期からの移り変わりは気温の変化が大きく、最もストレスを感じやすい時です 生活環境が変わる人も多く、気候への適応による身体的な負荷や、新しい環境で緊張することが増えて、不安、プレッシャーなど心身のストレスにつながる要素が多いので要注意です
また、加齢も交感神経が優位になる傾向があります これは年齢とともに副交感神経の働きが低下するためです 女性の場合、健康な状態を保つ作用のあるエストロゲンという女性ホルモンが年齢に応じて徐々に減少し、ホルモンバランスが崩れることによって自律神経の乱れが生じ始めます
夜型の生活習慣が身についてしまうと自律神経のバランスが乱れるだけではなく、私たちにもともと備わっている体内時計のリズムまでも乱してしまうので、ホルモンの分泌などの生体リズムもくずれてしまうことになりかねません 深夜に飲食するなどは、極力控えた方がいいと思われます
他には喫煙や過度の飲酒など、嗜好品の生活習慣が原因になることもあるようです
生活リズムの乱れが与える影響
ストレスが長く続いて緊張状態が慢性的になると、副交感神経のスイッチがなかなか入りません これは、仕事などで過度のストレスや緊張を感じることが多くなると交感神経が優位になり、休息モードに入るはずの夜になっても、副交感神経への切り替えが上手くいかないために起こることです 緊張状態になり夜の睡眠時も興奮モードが働いていると、当然うまく休めずに心身共に疲れた状態になります 例えば朝起きてもだるさが残っている、やる気が出ないなどの症状が出始めます これが積み重なるとバランスが乱れて、日中に仕事や学校に集中できなくなるなど、スイッチの切り替えがうまくいかずに不調に陥ってしまうというわけです
また、仕事が忙しく、イライラせかせかと緊張状態の時に食事をすると、交感神経が過度に働いているので胃腸の働きが抑制され、消化液の分泌も低下するので、胃もたれなどを引き起こしたりと、弊害も出てきます
私たちは毎日、普通に生活しているつもりでも、仕事や家庭生活の忙しさの中で緊張状態にあったり、睡眠がうまく取れずに質が悪かったりすると、疲労が蓄積して、知らず知らずのうちに交感神経が優位になる時間が増している状況に置かれています そしてその結果、休息やリラックス時に働く副交感神経の働きが抑えられてしまい、疲れがたまって様々な不調が現れるのです
身体の不調が続いている場合、自律神経が乱れている可能性を疑う人は少ないと思います 思い当たる原因がない場合は、自分の生活習慣を見直してみるといいと思います とはいえ、生活の中で上手に交感神経と副交感神経のバランスを切り替えることができているかどうかなんて、なかなか確かめようもないことだとは思います(^_^) ただ、自律神経の乱れはストレスの解消や生活習慣を改善することによって整えることができますし、セルフケアをするかしないかでも変わってきます 多くの方が自律神経の働きを意識しながら、過ごしていけたらいいなと思っています😊
さて、では生活リズムを乱さないためにはどうすればいいでしょうか?
ストレスを受けないようにする
とは書きましたが、ストレスは外部からの様々な心理的、感情的、環境的、物理的な物による負荷や不安や刺激により引き起こされます 自分でストレスをなくすのは難しく、ストレスが軽減するような生活を心がけるしかありません(^_^;) 自分の体力を超えた過活動の状態はストレスが増しますが、不活動の状態でも交感神経が低下して活性化しません ブレーキがかかった状態のままでは、体が怠く重いだけでなく、身体の細部の働きも低下してしまいます 前述したように、交感神経と副交感神経が共にバランスを取りながら上手に働くことが大切であり、結局はそのバランスが乱れないような生活リズムを整えることが必要とされます😊
自律神経の働きが崩れると交感神経の優位な状態へと傾きがちになるため、日常生活で意識的に副交感神経を高めて興奮モードを抑えるようにすると、それが自律神経のバランスを整えることにつながります
夜に寝付けなかったり、気持ちが高ぶっている時などは交感神経のスイッチを弱める方法をいろいろ持っておくといいと思います 各自リラックスできる方法は違うと思いますが、友達と話したり、音楽や映画鑑賞など好きな趣味に没頭したり、リラックスできる方法が多いほど自律神経の切り替えがスムーズになるので、皆さんも自分なりの方法を見つけましょう😉
生活する上で心がけること
忙しい日が続いた時はゆっくり休息をとることを心がけるといいと思います 就寝時間と起床時間を決めて、毎日きちんと守ることも生活リズムを整えるのには有効ではないでしょうか 先程、就寝時の話をしましたが、眠れない人はリラックス効果のあるハーブなどを使って湯船につかるのも一つの手ですし、副交感神経が優位になって眠りにつきやすくなる手段はたくさんあります そして、睡眠中に優位だった副交感神経を交感神経へと切り替えて、身体を活動モードにすることもとても大事なことです!
朝の光を浴びることは、実は身体にはとても重要なことのようです 体内時計のリズムは約24時間で刻まれていますが、これが乱れるとちゃんと寝たり起きたりできなくなります そして乱れた体内時計は朝日を浴びることによって毎朝リセットされます 朝の光は視床下部に信号を送りそれによって主時計がリセットされ、朝食をとることによって、末梢細胞にある子時計の体内時計もリセットされます 私もほとんど知らないことばかりでした ^ ^
そして、朝の光はいろいろなホルモンにも影響を与えるようです 私もホルモンに関して特別な知識があるわけではないので、こんなホルモンが働いているんだと頭に入れるくらいでいいと思います(^_^;)
私たちが光を浴びると神経伝達物質のセロトニンの分泌が促されます セロトニンは精神を安定させストレスに対して効能がある脳内物質ですが、日中にセロトニンがしっかり分泌されていないとメラトニンが正しく分泌されません 自然な眠りを促す働きのあるメラトニンが減少すると、夜眠れなくなったり睡眠の質が下がったりします 睡眠リズムを形成しているのは就寝時分泌される睡眠ホルモンメラトニンと、起床時に分泌されるオレキシンの2つのホルモンですが、朝の光を浴びる時間によってはメラトニンの分泌が遅れたり、不十分になったりします それによって、寝つきが悪くなるなど影響が出てきてしまうということのようです
また、夜は暗いと認識している体内時計に、明るい光は時刻を乱す原因となり得ます スマホやパソコンのブルーライトは目に見える光の波長の中で紫外線に近い青色の光で、体内時計を遅らせる効果が最も強い光だと言われています 本来なら寝ているはずの時間に光を浴びると、昼間の状態が続いていると認識して入眠しづらくなり、睡眠の質の低下を招きます なるべく就寝の2時間前にはブルーライトを浴びることを避けて快眠できるよう心がけましょう😄
そして、朝食をとることも体内時計のズレを改善するためには大切です 朝食をとると体内時計を管理する時計遺伝子が時を刻み始め、また、体内で熱が産生されて体温が上昇するのですが、朝食をとると血糖を下げるホルモンの効率が高まって、自律神経のバランスが整いやすくなるということのようです 朝食は抜かずに朝、昼、晩と3食規則正しい食生活を心がけるといいと思います😀
他にも、気分転換やストレス発散で心身をリラックスさせると血圧や心拍数が下がり、副交感神経が優位になります ストレッチや軽い運動をするのもいいと思います 血流が悪くなることも自律神経に影響を与えるので、座りっぱなしの方もストレッチで筋肉をほぐしたり、こまめな水分補給や入浴で血流をよくすることが自律神経を整えることにつながります
と、いろいろ呟いてみましたが、自分なりのできる範囲での休息の方法を見つけて、生活リズムを壊さないように心がけてみて欲しいと思います😊
※このページはアフィリエイト広告を利用しています
CMで話題!質の良い休息で毎日をサポート【アラプラス 深い眠り】